
メールでお問い合わせ
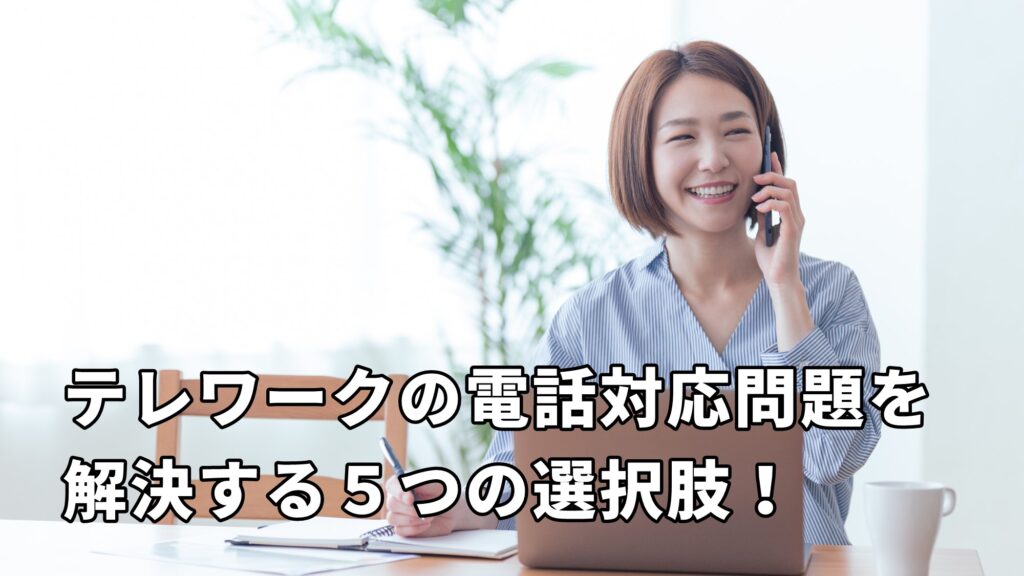
働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、2020年頃より広まったテレワークは、今でも多くの企業で導入されています。
時間や場所にとらわれずに、自宅やカフェなどで働けるスタイルは、交通費などの経費削減や通勤時間の短縮にもつながりますが、メリットばかりではありません。
特に、電話対応の面ではダメージとなるトラブルが起こりやすく、いくつかのデメリットがあります。
この記事では、テレワークの電話対応で起こりうる問題や対処策、便利ツールについて解説していきます。
\ テレワーク先でも会社の固定電話がスマホで使えるアプリ!/

ここ数年で普及したテレワークですが、まだまだ歴史が浅いためテレワーク自体への認識もはっきりしていないのではないでしょうか。
テレワーク中の電話対応を整備する前に、まずはテレワークとは一体どのようなものなのか、その定義を把握しておきましょう。
テレワークとは、本社などのオフィスから離れた場所で仕事をする勤務形態です。
「Tele=離れた」と「Work=働く」が組み合わさったキーワードで、時間や場所にとらわれずにさまざまなスタイルでの働き方の総称として用いられています。
一般社団法人日本テレワーク協会では、テレワークについて「情報通信技術を活用した、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方」として定義しており、働く側だけではなく会社側のコスト削減につながるとも公表しています。
さまざまな勤務形態をもつテレワークですが、主には以下の3種類があります。
テレワークの勤務体系
それぞれの勤務体系について、以下順に詳しくご説明します。
在宅勤務とは、自宅を就業場所とし、出勤せずに業務を行う勤務形態です。オフィスに出勤する社員とはインターネットなどの手段を使って連絡を取り合い、業務をこなしていきます。
在宅勤務のメリットは、通勤時間がなく時間の融通もききやすいため、時間を有効に使える点にあります。
モバイルワークとは、場所を特定せずに移動中や取引先などでパソコンや携帯端末などを使って、仕事をする勤務形態です。例えば、営業などの外回りが多い仕事の場合、わざわざオフィスに戻って作業をする過程が省かれるため、時間や労力の削減になります。
業務の効率化につながるのが、最大のメリットだといえるでしょう。
サテライトオフィス勤務とは、オフィスとは別の場所に設けられたオフィススペースや施設で仕事をする勤務形態です。例えば、社内LANがつながるスポットオフィスや、フリーWi-Fiが完備したレンタルオフィスでの勤務がよく見受けられます。
社員の家から近いスペースを選べば、通勤時間の削減につながって在宅勤務ほどではありませんが、時間の融通がききやすくなるでしょう。
テレワークを導入する企業が増加した背景には、政府が発表した働き方改革や2020年2月頃から拡大した新型コロナウイルスの影響などがありますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
働き方改革からの見解としては、テレワークの導入によるメリットとしては、以下の3つです。
まずテレワークの導入により、通勤時間や時間調整などの負担が減り、ストレスや疲労が軽減するといったメリットが考えられます。
それと同時に、会社側はオフィスの賃料や社員に支払う交通費を削減できるといったメリットもあるのです。
新型コロナウイルス感染拡大対策の観点では、オフィス出社の機会を減らすことで密を避け、感染を防止できるといったメリットがありました。
こうしたメリットがある中で、調査信用会社の東京商工リサーチが実施した「第10回・新型コロナウイルスに関するアンケート調査(2020年11月25日)」においての「在宅勤務・リモートワークを現在も実施している」の回答では、以下のような結果が出ました。
東京商工リサーチ 第10回「新型コロナウイルスに関するアンケート」調査
参照:https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1190292_1527.html
また、パーソルキャリア株式会社が行った調査(2021年1月実施)においては、「今後もテレワークを継続する」と回答した企業は、全体の60%だったと公表されており、思うほどにテレワーク推進や継続が状況が伺えます。
転職サービス「doda」、採用担当者約1,000人に「第2回自社のリモートワーク・テレワークに関する調査」を実施~リモートワーク・テレワークを今後も継続すると回答した採用担当者は約6割。前回調査から10.5ポイント増加~
参照:https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2021/20210322_02/
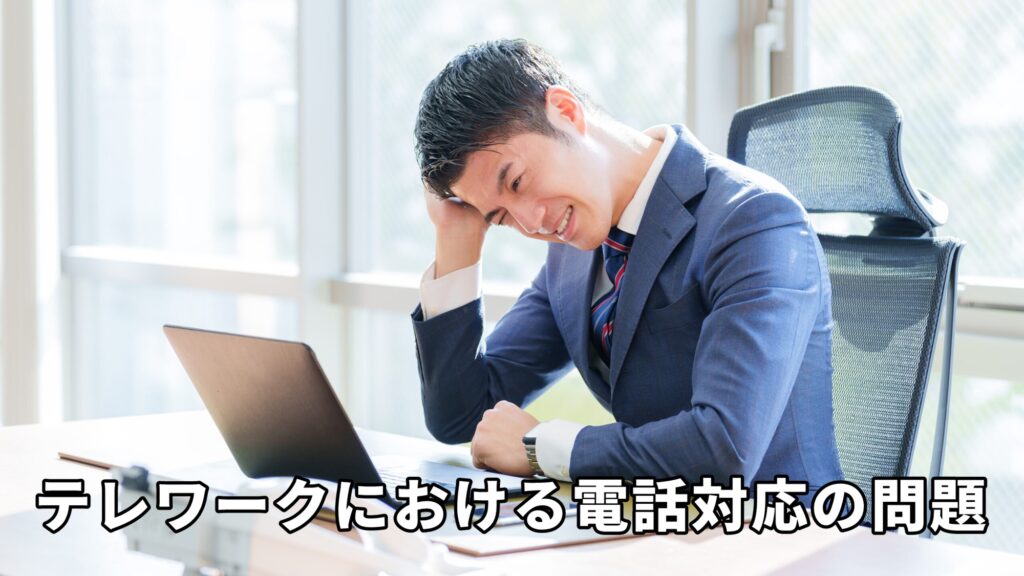
業務の効率化や時間や場所にとらわれず働ける事柄の時間の有効活用など、多くのメリットがあるテレワーク。
しかし、電話対応においてはいくつか問題が生じます。主に、発生する電話対応の問題としては以下2つが起こり得ます。
それぞれがどのような問題なのか、以下順にみていきましょう。
テレワークには、顧客やお客様からかかってきた電話に対する対応速度が低下するという問題が存在します。
テレワークの影響によって顧客などからの電話が折り返し連絡対応となってしまうことで、対応速度がダウンします。
対応速度がダウンすると、顧客からの信頼度が下がってしまう可能性が高いですし、商談などの機会損失にも繋がりかねません。
テレワーク中の電話対応の対策として、当番の社員を出社させるという方法もありますが、交代出社による社員の負担が大きくなるといった問題が発生します。
また、顧客などからの電話取次業務も発生し、テレワークによって当番の社員と担当者間でコミュニケーションがうまく取れず、社員同士のストレスが増える可能性があります。
また、電話対応や取次業務と並行して別の業務も行う場合は、メインの業務が進まず、業務効率の低下につながりかねません。
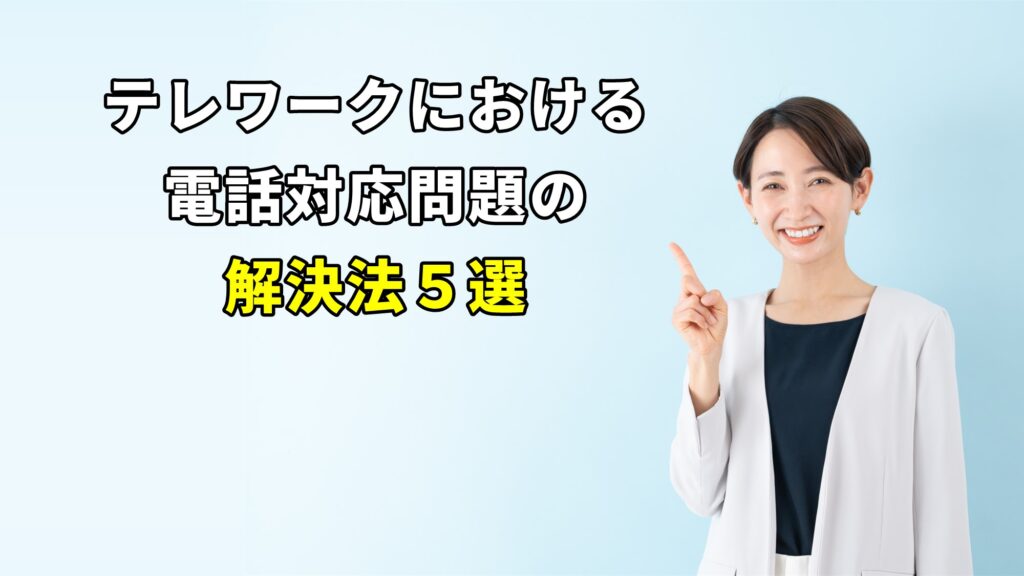
電話対応という面においてテレワークには「対応速度の遅延」や「社員の負担増加」といった問題が発生あります。
この問題によって顧客の信用度低下やビジネスチャンスを逃すなど、会社としての損失に繋がる恐れがありますので、テレワーク環境を整備するうえで電話対応の問題は未然に防ぐ必要があります。
テレワークにおける電話対応の問題を防ぐ方法として、代表的なものは以下5つが挙げられます。
それぞれがどのような方法なのか以下順にご紹介します。会社の損失を防ぐだけでなく、ビジネスチャンスを逃さないためにもふさわしい手段でしっかりと対処していきましょう。
テレワークにおける電話対応問題を解決する方法の1つ目に、シンプルに「担当者が折り返し電話をする」手段があります。
会社の固定電話にかかってきた電話をオフィスで待機中の社員が対応し、担当者へ取り次いだ後、担当者が顧客に電話をする流れです。
折り返しに使う電話機は会社の固定電話ではなく、担当者が所有するスマホや携帯電話になります。
この方法では、特別なツールや費用などが要らず、すぐに取り入れられるのがメリットです。担当者が携帯電話を持っていれば、難しいことをせずに始められます。
しかし、この方法には電話対応の遅れや伝達ミスなどのリスクがあります。また、携帯電話を使用するため、相手先に不審に思われたり、個人の番号が知られてしまうというリスクもあります。
ビジネス上のやり取りでは信用度も重要な要素のため、携帯電話で折り返す方法はあまりおすすめできません。
テレワークにおける電話対応の問題を解決する方法の2つ目に、会社宛の着信を、別の電話番号へと転送する「電話転送サービス」を利用することが挙げられます。
電話転送サービスとは、契約中の電話回線にかかってきた着信を、別の電話番号へと自動的に転送し転送先の電話端末で応答できるサービスです。
電話転送サービスを使って社員の携帯電話番号を転送先に設定しておけば、オフィス以外の場所にいても担当者がその場ですぐに対応できるのがメリットです。
また、オフィスで社員が待機する必要性がなくなるため、出勤の手間や経費を省けます。
電話転送サービスによっては、曜日や時間などによるサービス利用時間を設定する使い方もあります。
ただし、あくまで着信を転送するだけなので、転送先の携帯電話から会社の番号で発信することはできません。また、携帯電話へ転送した場合、別途1分あたり20円程度の通話料金がかかりますので、転送しすぎるとコストが増加してしまいます。
転送電話サービスを利用するにあたって、「折り返しの発信はできず、転送するのに別途料金がかかる」という点に注意しましょう。
テレワークにおける電話対応の問題を解決する3つ目の方法として、スマホ内線化アプリを導入することが挙げられます。
スマホ内線化アプリとは、会社の固定電話とスマホアプリが連動し、スマホを会社の内線電話機の1つとして使えるようにするアプリケーションサービスです。
スマホ内線アプリを使うことで、テレワーク中も会社の電話がスマホで使えるようになり、オフィスにいるときと同じ感覚で対応することが可能になります。
また、スマホアプリから会社の電話番号で発信することもできるので、まさに会社の電話機をテレワーク先に持ち出していると言えます。
オフィスに常駐するスタッフも不要になりますし、会社の電話に顧客から問い合わせがあってもスマホで即応答することができるため、取次による対応速度の遅延も生じません。
手軽にテレワーク中も会社の電話をスマホで使えるようにしたい場合は、スマホ内線化アプリがおすすめです。

テレワークにおける電話対応の問題を解決する4つ目の方法としては、電話代行サービスを利用することが挙げられます。
電話代行サービスとは、代行業者のスタッフが従業員に代わって着信した電話に対応してくれるサービスです。
電話代行サービスを使うことで、会社の電話対応を代行業者に丸投げすることができ、必要性に応じて従業員が折り返し電話をする流れで行われます。
これによってオフィスでの社員待機に必要なコストが削減されますが、サービス業者への費用が発生するので、完全にコストが削減されるわけではありません。
ただし、折り返し対応が多くなるほどに電話対応の遅れが見込まれるので、すべての対応が早くなるわけではない点を頭に入れておいた方がよいでしょう。
テレワークにおける電話対応の問題を解消する5つ目の方法として、クラウドPBXというサービスを利用することが挙げられます。
クラウドPBXとは、クラウド上に電話回線とPBX*を設置し、インターネット経由して利用者の電話端末とクラウド上の電話回線を接続することで、通話を可能とするIP電話サービスです。
「クラウドPBX」を導入することで、会社に固定電話回線を敷設する必要がなくなり、テレワーク先でもインターネット環境さえあれば会社の固定電話が使えるようになります。
通話端末も電話機に限らず、スマホやパソコンでも利用可能なため、どんな場所でも会社の電話が使えるのはクラウドPBX最大の魅力です。
ただし、クラウドPBXにも以下のようなデメリットが存在するため、利用者を選ぶサービスである点に注意しましょう。
特に、既に会社の固定電話がある場合、クラウドPBXを使うには番号ポータビリティという番号移行手続きを行う必要があるのですが、移行先のクラウドPBXが会社の市外局番エリアに対応していないと移行が出来ません。
番号ポータビリティできる場合でも、移行手続きには「時間」と「手間」と「費用」がかかるため、おすすめできません。
「会社の電話番号が変わってもいい」「そもそも会社の電話番号が無い」という方には、テレワークの電話対応問題を解決策としてクラウドPBXをおすすめします。
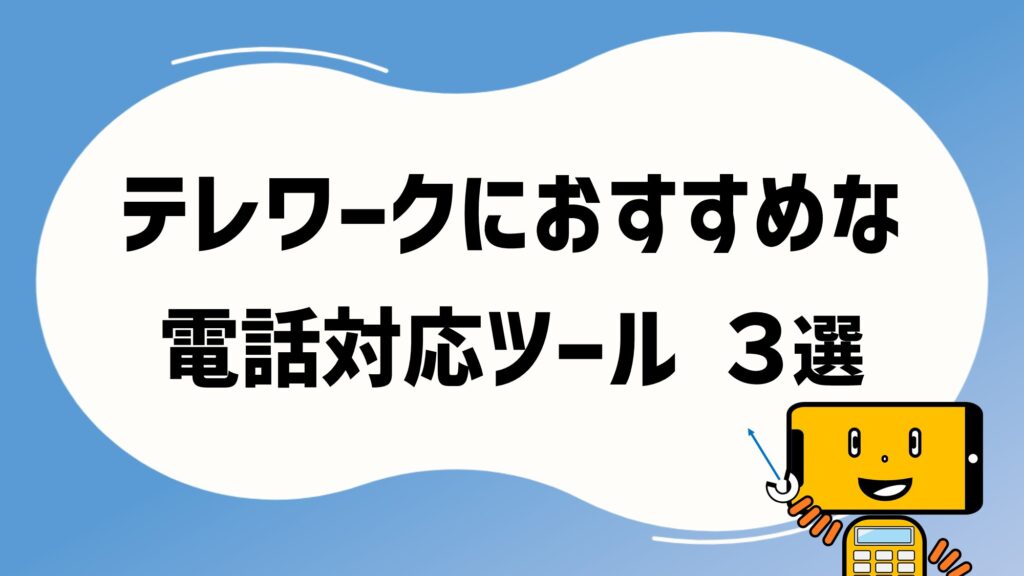
ここまでテレワークにおける電話対応の問題を解決する方法についてご紹介しましたが、その方法には具体的にどのようなサービス・ツールがあるのでしょうか。
ご紹介した方法のうち「スマホ内線化アプリ」と「クラウドPBX」の中から、テレワーク中の便利な電話対応ツールを以下3つご紹介します。
電話対応の問題で悩んでいる方は是非参考にしてみてください。
「テレワープ」とは、株式会社フォレスタが提供する「今使っている固定電話をそのままに、スマホでも発信・着信できるようにするスマホ内線化アプリ」です。
テレワープ最大の特徴は「今使っている会社の電話がスマホでも発信・着信できるようになる」点です。その他にも以下のような特徴があります。
テレワープなら、固定電話を継続利用しつつスマホでも発信・着信できるようになるため、電話番号や電話機が変わることはありません。
その他にも、「時間外ガイダンス」や「内線通話」、「保留転送」など高度な電話機能も標準で付帯されているため、テレワークに限らず電話対応を円滑にすることが可能です。
今使っている会社の固定電話をそのままテレワーク先でも使いたいという場合には、テレワープが最適でしょう。
テレワープの評判や口コミについて、気になる方はこちらをご覧ください。


03plusは、株式会社グラントンが提供する「03番号や06番号など主要なエリアの市外局番をスマホで手軽に使えるクラウドPBXサービス」です。
03plus最大の特徴は「スマホ1台からでも利用できるリーズナブルな商品設計」です。月額料金も1,078円/1ID(税込)からと、小規模事業者でも導入しやすくなっています。
その他の特徴としては、以下の通りです。
03plusはスマホだけで手軽に固定電話の番号を取得できるので、これから会社を新設するけど、基本的にはテレワークで運用するといった企業や個人事業主におすすめです。
反対に言うと、既存の固定電話番号が引き継げない場合があるため、既に会社や事務所に固定電話があるといった場合にはテレワークツールとして03plusを導入するには番号変更が伴いますので注意しましょう。
03plusの評判や口コミについて、気になる方はこちらをご覧ください。
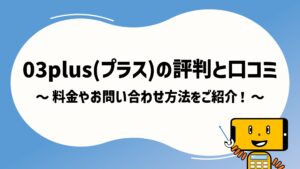

MiiTelは、株式会社RevCommが提供する「AI搭載によって顧客対応や営業電話の可視化などの分析ができるクラウドPBXサービス」です。
MiiTelの特徴としては、何といっても「AIが搭載されている」点でしょう。具体的には、電話の顧客対応や営業電話の内容をもとにAIが解析をし、改善点の提案をする機能があります。
また、電話の内容の録音や文字起こしする昨日もあり、分析結果とともに社内で共有できるのも魅力です。
月額料金が5,980円〜と、クラウドPBXの料金相場の中では高めの設定にはなっていますが、AI搭載の部分を含めると適切な料金設定です。
「カスタマーサポートをテレワーク中も行いたい」などの、コールセンター用途をテレワーク先に持ち込みたい場合はMiiTelがおすすめです。
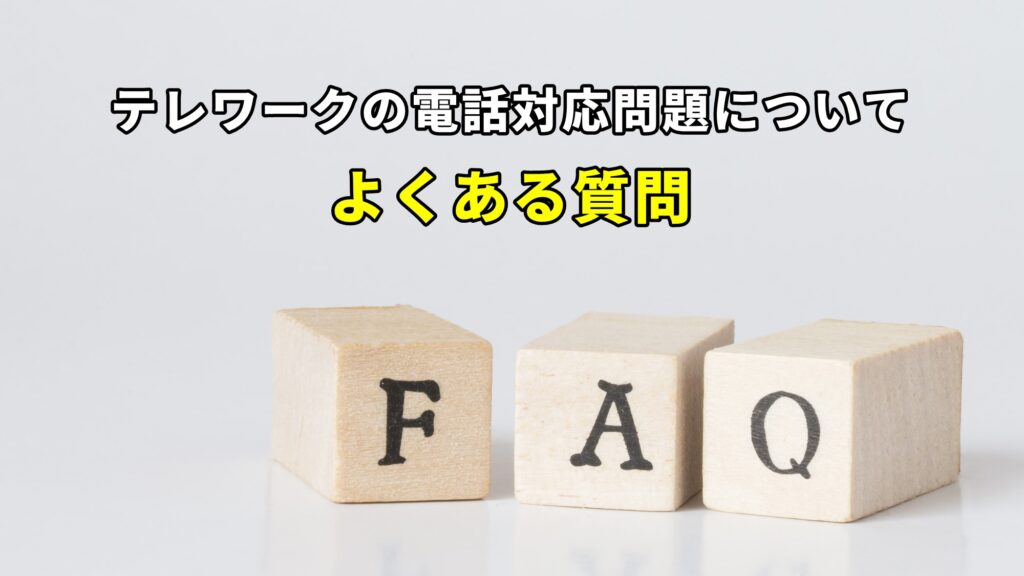
テレワークでの電話対応に関する問題を防ぐための方法には、担当者のスマホでの折り返し、転送電話サービスの利用、スマホ内線化アプリの導入、クラウドPBXの利用などが挙げられます。
ここでは、これらの方法に関連したよくある質問を以下にまとめましたので、参考にしてください。
テレワークにおすすめの電話アプリを3つご紹介します。
| テレワープ | SUBLINE | テレワークCall.app |
|---|---|---|
| テレワープは、固定電話に手のひらサイズの装置を繋げることで、固定電話とスマホアプリが連動し、スマホでも固定電話の発信・着信が行えるサービスです。 今使っている固定電話がそのままアプリと連動する部分がテレワープ最大のポイントです。 導入も非常に簡単で、小さな装置の設置とアプリのインストール・初期設定だけなので、誰でも手軽に利用できます。 | SUBLINEは、アプリをスマホにインストールすることで、ビジネス用の050電話番号も持つことができるサービスです。 特別な装置や初期費用は不要で、携帯電話や固定電話などの煩わしい手続きも不要です。 そのため、簡単に導入でき、最短で即日から利用を始めることができます。 | テレワークCall.appは、テレワーク中でも安全にお客様と電話ができるアプリです。スマートフォンや携帯電話で通話可能なので、場所を選ばずに電話対応ができます。 全員が忙しくても、コールバックリストに登録されるので、後から時間を見つけてお客様に折り返しできます。 通話料金は会社が負担するので、個人の携帯電話には負担がかかりません。 さらに、社員の個人電話番号がお客様に知られることはありませんので、社用携帯を所有していない方でも安心です。 |
テレワーク中に電話を転送するには、まず転送元の電話番号を契約している通信会社に申し込む必要があります。
転送サービスを利用することで、会社にかかってきた電話を別の電話に自動的に転送することができ、これによりテレワーク中でも効率的に電話に応対できます。
なお、キャリアによって申し込み方法が異なり、利用開始までに時間がかかる場合もありますので注意が必要です。
転送サービスを利用すると追加料金が発生する場合があるため、その点も注意してください。
クラウドPBXと電話転送サービスには「転送費用」に違いがあります。
電話転送サービスでは、転送するたびに費用が発生しますが、クラウドPBXでは転送にかかる費用がありません。
したがって、電話を受ける回数が多いと、コストに大きな違いが出ることがあります。
また、電話転送サービスでは、スマホに転送元(例: オフィスの固定電話)の番号が表示されますが、クラウドPBXでは発信者の番号がそのまま表示されます。
これにより、相手の番号を見て、事前に誰からの電話かを判断できるため、より柔軟な対応が可能です。
テレワークのメリットや電話対応で起こりうる問題、そしてその対処法について解説してきました。
働き方改革と新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年頃から急速に浸透したテレワークですが、メリットがある反面、多少のデメリットもあります。
スムーズな取引やコミュニケーションに向けて、テレワークには取り組む課題が残っているのが正直なところでしょう。
解決策が見つからずお悩みの方にこそ、今回ご紹介した対処法や便利ツールを活用してより良いテレワークを実現してみてはいかがでしょうか。